「エビハラさん、うちも中途社員に加えて、新卒社員も取り始めたのですが、
自分の息子以上に年が離れた社員たちを前に、正直なところ、とまどってまして・・」
社会的にも「多様性の尊重」が叫ばれる中、新入社員をはじめ様々なタイプの社員
が混在し、会社組織やチーム作りの苦労話を聞く機会も増えてきています。
経営者として、会社組織と個人の優先順位に板挟みになっている姿は、
大なり小なり、そこかしこで見られる風景になっているようです。
その延長で、「多様性の尊重」という言葉に、そろそろ辟易としている経営者も
いらっしゃるのではないでしょうか。
多様性は創造力の源泉になる
本質的には、特に答えが見出しにくい状況下において、多様な視点で物事を捉え、
成長に向けた方向性を見出していくことは、非常に強力な武器になります。
特に、次のステージへのブレークスルーに重きを置くビジネスにおいては、
社員のバックグラウンドや特性が偏って、発想が硬直化しないように、
すでに採用の段階から、多様性を重視した組織づくりに注力しています。
(コンサルティング会社もその一例です)
しかしながら、単に多様な人材をそろえるだけでは、成果にはつながりません。
多様性を活かす前提として、何が必要なのでしょうか?
多様性をたばねる共通基盤の存在
単なる「多様な人材」の集まりだと、単に「まとまりのない組織」となり、
放置しておくと、最悪、組織崩壊に向かっていきます。
特に欧米系のグローバル企業では、人種・国籍・宗教等がバラバラな人たちが、
会社組織の中で、一緒に協力して仕事を進める必要があります。
ゆえに、大前提として、共通のビジョンや価値観、仕事の進め方を明文化し、
何度も何度も繰り返し、刷り込みを行う仕組みを構築・維持することで、
組織としての能力、ビジネスの競争力を向上させてきました。
共通の組織風土づくりが不要な日本の会社と、その限界
対する日本は、戦後の高度経済成長からバブル景気に代表される時代を通じて、
極めて均質化された人材の集団が、村社会的な阿吽の呼吸で強力に走り続けて、
ジャパンアズナンバーワン、とまで言われる成功体験を積んできました。
その後「失われた30年」と言われるまで時代が流れましたが、
根本的には、今でも「全員が同じ価値観を持ってほしい」という甘い期待感で、
組織運営にあたってきたのが、多くの企業の実態ではないでしょうか。
そして昨今、いよいよ労働力が不足し、
新しい世代や属性の価値観を尊重しないと、労働力が確保できなくなり、
あわてて、表面的に多様性を尊重するポーズをとるようになったが、
それが限界を迎えつつある、という実態もあります。
多様性の尊重による、組織崩壊の危機
では、会社としてはどうすれば、昨今の情勢に適応できるのでしょうか。
まず第一に、会社とビジネスがめざすビジョンや目的、そのために必要な価値観、
全員に求める行動規範や判断基準といったものを、明確な言葉で定義し、
継続的に啓蒙する仕組みを構築する必要があります。
それに基づき、業務のプロセスが本来目指すべき方向性に合致しているのか、
組織の構造と役割、意思決定のプロセスと権限等のルール整備も不可欠です。
その上で、社員への情報展開やコミュニケーション、
一人ひとりに求められる行動や達成基準についての相互理解、
その下支えとなる人事の制度や仕組みの整備、
そして社員の成長を支援する教育、価値観を共有できる社員の採用、
といった、有機的に関連する要素のシステム化が求められます。
「規律×尊重」の掛け算の重要性
まず会社としての「型」があること、これが大前提です。
「型」があった上での、多様な個性による味付けが、会社の成長につながります。
まず「型」を身に着け、自分なりに発展させ、ついには「型破り」の域に到達する。
「型」なくしての勝手な個性は、単なる「型無し」として、相手にされません。
組織運営においては、越境や異論は歓迎しつつも、逸脱は素早く矯正する。
「尊重だけ」では甘さに流れるが、「規律だけ」でも硬直してしまう。
「規律×尊重」の掛け算を、経営者が順番通りに設計すること。
これが、多様性を真に機能させるための、大前提となる土台になります。
あなたの会社では、多様性を律する共通の規律/価値観が浸透していますか?
文責:蛯原 淳(えびはら じゅん)

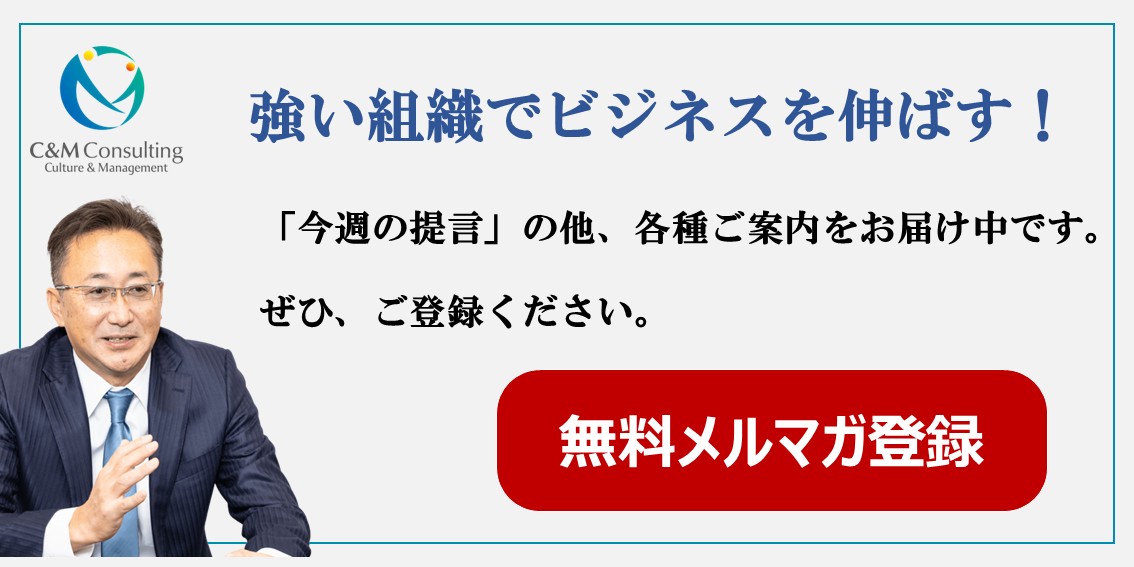


コメント
COMMENT