「企業文化、組織風土、社風、とか、どれも抽象的過ぎて、
ビジネスで儲かる感じ、がしないんですよね。」
とある経営者の方からいただいた、率直なコメントです。
たしかに、ビジネスの一般的な数値管理と違い、風土は可視化が容易ではありません。
それゆえ「やってもやらなくても成果が見えない、だから意味がない」となりがちです。
では、「強い組織風土」というのは、単なる抽象的な夢物語なのでしょうか。
ここでひとつ、皆さんに質問です。
「強い組織風土」が競争力の源泉になっている組織って、何か思いつきますか?
私からは、3つの組織を挙げたいと思います。
軍隊、宗教、暴力団、です。
1)軍隊
日本の自衛隊の方々の組織力の高さは、各国の軍隊も認めるところですが、
技術的な練度の高さもさることながら、各部隊の行動力を支える大きな強みは、
自衛隊という「組織風土」の強靭さにあります。
そして、この「組織風土」は、決して自然発生的にできるものではなく、
作戦の成功に必要な組織の風土は何なのか、本質的な要素を過去の実績からも学び、
24時間365日かけて、隅から隅まで徹底的にコントロールしています。
高等工科学校や防衛大学校での全寮制教育でも、組織の風土を体得させることが、
入隊後の組織力の向上に大きく寄与することを、歴史的に継承しています。
自衛隊の方々と接すると、瞬間的に「空気が違う」と感じるのは、
数字では示すことができない、組織としての強さ、ではないでしょうか。
2)宗教
とても幅の広い概念ですので、断片的な例にとどめますが、
オウム真理教は、日本の近代史上、ある意味最も成功したカルト集団だったと言えます。
その強さの本質は何だったのでしょうか?
私はそこに「組織風土」の底知れぬ強さ、恐ろしさを感じました。
オウム真理教に代表される、異常に求心力の高い宗教団体においては、
往々にして、その組織独特の使命感と一体感を高めるための、
類稀なる工夫と「仕組み」が、組織活動のあらゆる場面にビルドインされています。
単に、カリスマ性の高い教祖が、熱心に語り続けるだけではありません。
信者の候補者を採用して、育てて、活躍の場をあたえ、信賞必罰で報いる、
一連の「仕組み」が、組織全体で回っていることが、強さの本質でもあり、
外部の雑音に負けない、強力な「組織風土」の形成を、確かなものにしています。
3)暴力団
あくまでも、学習のための参考材料としてですが、
組織を率いる経営者にとっては、学べる点が随所にあります。
組員はなぜ、幹部の想いを十分に汲んだ(大いなる忖度を含む)言動を取れるのか?
なぜ、組織に対して献身的に、時には刑務所務めも厭わずに貢献するのでしょうか?
トップが望む姿についての、強烈なコミュニケーションだけではありません。
組織上のヒエラルキー、権限、レポートライン、会議の実施形態、情報の展開方法、
キャリアパス、金銭的・非金銭的な報酬、お互いを認め合う文化、等々。
あらゆる「仕組み」が、組織の事業計画・活動目的を、
強力に加速させるような「組織風土」の実現のために、
合理的に設計され、長い年月をかけて熟成されています。
もちろん、社会情勢やビジネス環境、若手の意識の変化も踏まえて、
その「組織風土」と「仕組み」をアップデートし続けることは、一般企業と同様です。
今も非常にしたたかに、フロント企業にシフトしつつ資金源を育てているのは、
単にビジネスモデルの独自性(剛腕性?)が高いから、だけでなく、
ユニークな事業戦略を実行可能な、強い「組織風土」の存在こそが、競争力の源泉です。
以上、3つの組織、やや極端な例に聞こえたかもしれませんが、
いずれも、事業の実行に最も適した「組織風土」をデザインして、
徹底的にコントロールしている、という共通点が見えます。
そして、そうやって作り上げた「組織風土」を有することで、
たとえ仕事の内容が多少変化しても、「組織風土」の強さで勝てる、といえます。
(「戦略は組織に従う」と言うと、ちょっと大げさでしょうか?)
自衛隊は、災害時の救援・炊き出し・医療支援、海外PKO活動、
邦人・医療物資の緊急輸送、地域への社会貢献活動、等々で、
日々、卓越した活躍・貢献をされています。
オウム真理教は、パソコン販売やシステム開発(例:マハーポーシャ)、
健康食品ビジネス等でも、大きな収益をあげていました。
暴力団は、不動産、建設、飲食、イベント、風俗、投資等々、
自らに専門スキルが無くても、剛腕を発揮して事業範囲を拡大しています。
あなたの会社は、事業環境が変わっても勝てる「組織風土」になっていますか?
文責:蛯原 淳(えびはら じゅん)

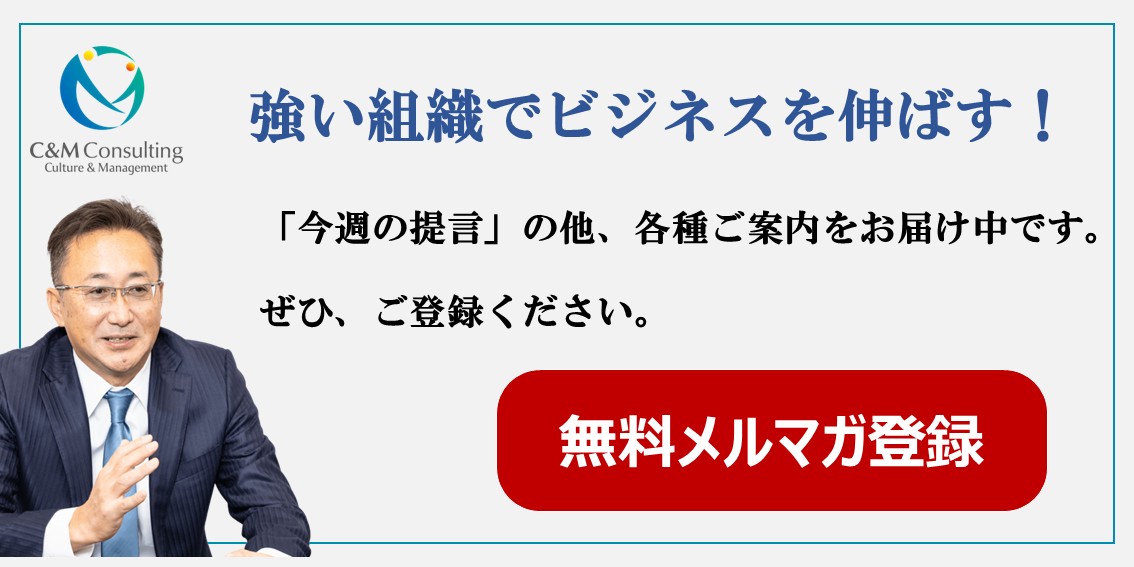


コメント
COMMENT