「うちも評価制度を導入したけど、なんか入れる前と変わった感じがしないんだよね」
そうつぶやくのは、最近社員も増えてきて、
「そろそろきちんとした評価制度を持たなきゃいけない時期ですね」
と社労士の先生にもアドバイスされて、まじめに取り組んでいるB社長です。
社員の採用面接でも、「私が入社したら、どのように評価されるのでしょうか?」
と聞かれることも増えてきて、きちんと制度を整えたので、
これで胸を張って答えられる、募集要項にも記載できる、と思っていた矢先でした。
よくよく話を聞いてみると、評価制度を導入すること自体に、
少し前のめりになっていた感があり、目的と手段がすり替わってしまう、
典型的なパターンのように思われました。
しかし、B社長のようなケースは決して少なくないようですので、
評価制度の導入で、一般的にありがちな落とし穴を3パターン、ご紹介します。
【落とし穴その1】 評価項目が言行不一致
主に「行動」や「能力」的な評価で起きやすいことですが、
経営者や職場での日常で会話されていることと、評価の項目が一致していない、
というケースは、多々見られます。
原因としては、
- 経営者の理念に基づいて評価項目を設定したものの、
その理念自体が管理職層に浸透していないため、ギャップが起きている。 - 外部のコンサルタントから、非常によく整理された評価項目の体系を提供されたが、
職場で上司が日常的に使っている視点とは、ミスマッチが大きい。
いずれも、評価項目が「評価の世界だけ」に閉じていて、
日常生活での会話に登場してこない、
結果として、評価の時だけ使う尺度になっている。
評価される側も、
「そんなこと、普段は何も言ってなかったのに、突然言われるのはおかしい!」
と不満を増幅させてしまいます。
【落とし穴その2】 目標達成度への過度のこだわり
期初に、個々人が1年間の業務上の目標をいくつか設定して、
期末にその達成度を評価する、昔からある手法です。
しかし、これも運用を間違えると、逆効果になってしまうので、注意が必要です。
よくあるケースとして、
- 自分の目標に入っていないことには、手を出さなくなる。
その結果、突発的な三遊間のゴロが発生してしまい、誰も拾わない。 - 期末が近づくと、自分の目標の達成度を上げることに夢中になり、
無理なお願いやゴリ押しが、職場や顧客に対して横行してしまう。 - 目標の達成度が低くならないように、簡単な目標しか持ちたがらなくなり、
結果として、困難な目標にチャレンジしている人がバカを見る。
といったことは、大企業でもよく見られる風景です。
良かれと思って導入した目標管理制度が、運用ひとつで大きく逆効果となるので、
制度を導入すれば安心、とは全くなりませんね。
【落とし穴その3】 評価すること自体が、目的化してしまう
評価とは、何のために行うのでしょうか?
給与に反映させるため、昇格の判断材料にするため、人材育成のため、
配置転換を考えるため、等々、いろいろあるでしょう。
評価のタイミングだけでなく、日常の業務の中で、
評価につながるポイントをこまめにフィードバックしてあげることも、
業務を円滑に進める上では重要です。(もちろん、評価の納得度向上にも)
しかしながら、評価した結果が、本来の目的に有効に活用されないと、
評価する労力ばかりが負担となり、評価された側にも不満が残るばかりでは、
逆効果で、やらない方がよかった、ということにもなります。
あるいは、評価を通じて、メンバーたちの人物的な見極めや批評を行い、
評論家的に悦に入ってしまう、自己満足系の評価者も多く発生します。
いわば健康診断とも似ていて、健診データの結果自体にはあまり意味はなく、
その結果を踏まえて何をするのか、再検査、投薬、食事の改善、運動習慣の定着等、
それらのアクションにこそ、健康診断の価値があるはずです。
評価制度も同じで、評価内容それ自体には、大した価値はなく、
そこからのアクションにこそ、評価を行った価値が創出されるはずです。
あなたの会社の評価制度は、
顧客・取引先・経営者・上司・本人にとって、何の役に立っていますか?
文責:蛯原 淳(えびはら じゅん)

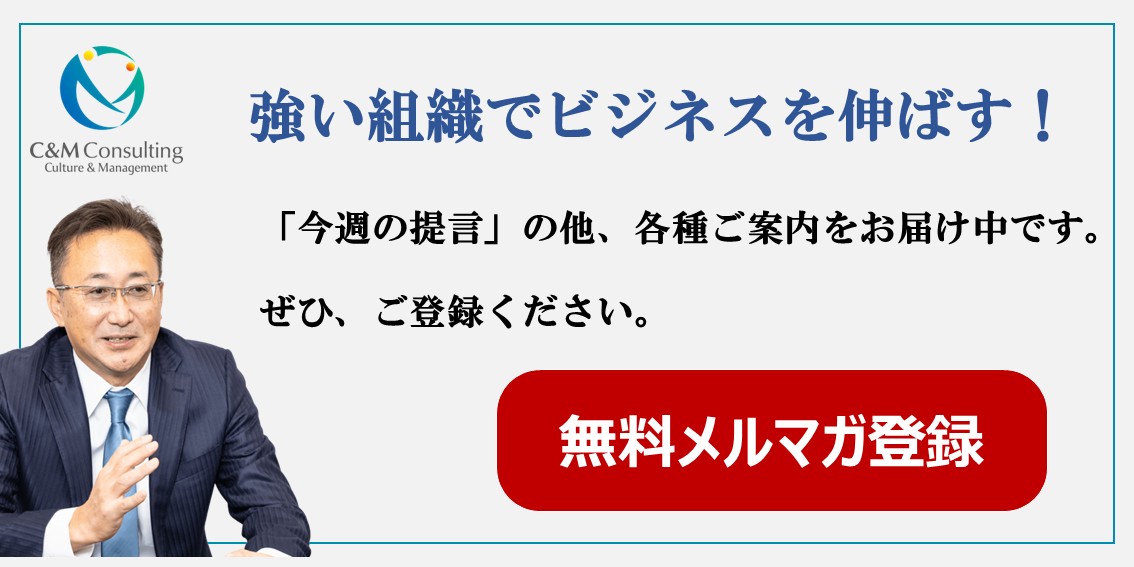


コメント
COMMENT