お盆休みで多くの社員が夏休みを満喫する中、さまざまな理由から、
仕事をすることを余儀なくされた社員もいたかと思います。
製造ライン停止中のメンテナンス業務、顧客からの緊急トラブル呼び出し、
急な自然災害による影響対応、等々、ごく普通の家族との夏休みがままならない。
そんな社員の気持ちは、実際に経験した方でないと、
なかなかリアリティをもって感じにくいものです。
それでも、みんなが休んでいる間に、会社のために、仕事のために、
時間と労力を提供してくれた社員は、本当に報われたと感じていますでしょうか?
経営者としては、「職務上、当然のこと」という気持ちはあるでしょう。
しかしながら、本人たちの感情的な納得感は、
「職務上、当然のこと」だけでは、なかなかスッキリと片付いていないものです。
ましてや、家族がいるとなると、親戚や知り合いの家族と比べられてしまい、
配偶者やお子さんたちの不満を一手に引き受けるのも、その社員の役割となります。
そして、お盆休み明けに、他の社員たちが、
「どこに旅行に行ってきた」「何して遊んできた」と楽しそうに談笑するのを横目に、
その社員だけが寂しい思いをするというのは、組織としても避けたいものです。
経営者としてできることは、何でしょうか?
1)おカネ
「休日休暇勤務手当で割り増し賃金を払ったり、緊急対応手当も出しているから、
問題ないじゃないか。会社として、やるべきことはやってるはずだ。」
たしかに、間違ってはいませんし、これはこれで重要です。
しかし、「カネさえ払ってればいいのか?」という疑問はぬぐえません。
実際、休日勤務を余儀なくされた社員が、おカネで不満を小さくできても、
満足するということはあり得ません。
そして「カネの切れ目が縁の切れ目」というリスクを背負いながら、
組織を運営していくことになってしまいます。
2)感謝
「私は本人に直接、言葉をかけて労をねぎらっているよ」という方もいるでしょう。
とても良いことです。しかし、それで本当に十分でしょうか?
特に、不満を感じている社員からすると、話を聞いたふりはするけど、
「表面的な言葉だけで納得すると思うなよ」と感じていることも多いものです。
(相手との信頼関係次第ですが・・)
社長には「いえいえ、仕事なんで当然っすよ」と言いながら、
社長がいなくなると「ちっ、いい気なもんだな」と唾を吐く、面従腹背の誕生です。
「とりあえず感謝しておいた」という表面的な姿勢は、
相手には100%バレますので、逆効果にもなりかねません。
3)認知
気遣いが上手な経営者は、皆が知らないところで頑張ってくれた社員のことを、
皆に知らしめてあげることを、意図的にやっています。
「Aさんが緊急対応をしてくれたおかげで、B社からの信頼が高まった。
大変だったと思うけど、おかげで次の展開も開けるかもしれない。」
人前でほめるか、陰でほめることに徹するか、方法はいろいろあれど、
本人にとっては、社長から直接ほめられることもさることながら、
周りの身近な人たちから、その貢献を認められ、声をかけられる方が、
その後の職場での日常生活の観点では、うれしいことが多いものです。
人は、その存在を認められることで、その場所にいる意義を感じます。
社員同士が、その貢献と存在を認め合える職場の風土をつくれると、
社員は、組織と仕事に対する帰属意識が高まって、
よりよいパフォーマンスを発揮するようにもなります。
あなたの会社は、休暇中に働いた社員の貢献が認められ、
十分に報われるような、組織の風土になっていますか?
文責:蛯原 淳(えびはら じゅん)

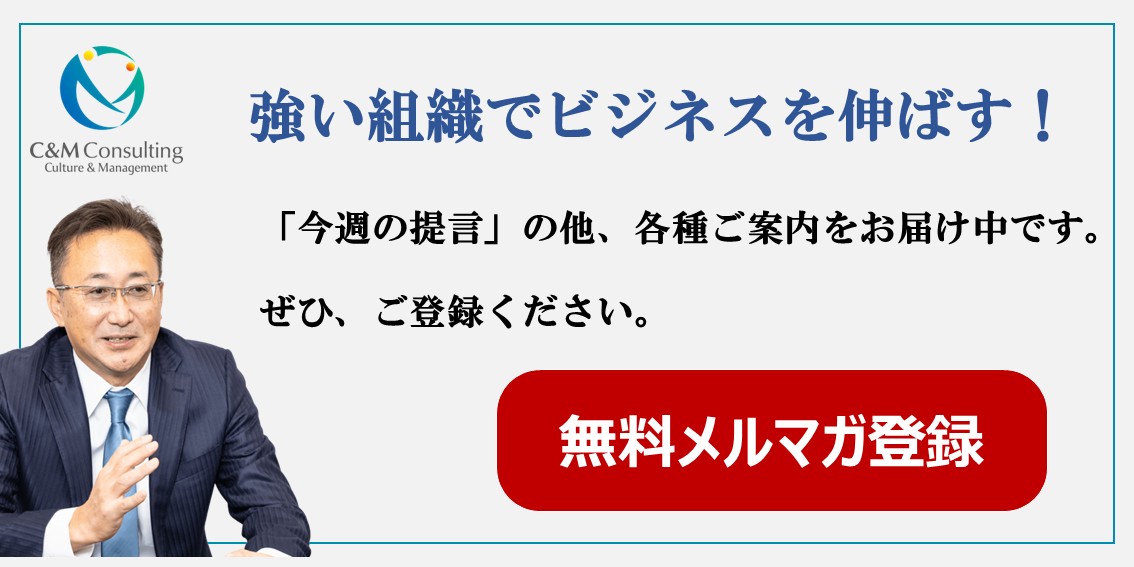


コメント
COMMENT